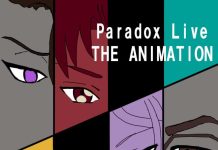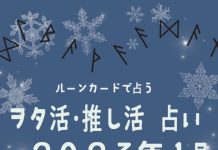この記事は、小説・漫画等の創作活動をしたい方にすすめる内容となっています。ですが、とくに創作活動をしていないアニメファンの方でも読めるように書いています。
各アニメの感想・レビューは、担当されているライターさんがいますので、そちらをどうぞ。
“詳しいこと”はスタートライン
『ゆるキャン△』はアウトドア趣味を、『ラーメン大好き小泉さん』はラーメンを題材にした物語です。
このような“何かものだったり趣味だったりをテーマ”にした作品を描く場合、それに関する詳しい情報(知識)が登場するのは大前提です。
ちょっと調べた程度でわかるような情報だけを羅列したのでは、底の浅い作品になってしまいます。
かと言って、詳しいネタを出すだけでは雑学書やwikiで十分!ということになってしまいます。
じゃあどうするの?
このような作品において最も大切なのは、キャラクターだと筆者は考えます。
テーマに関わるキャラクターを
アウトドアやラーメンに関する詳しい知識ネタを出す時、それを面白く、かつエピソードの中に不自然なく出すことが理想です。それを可能にするのが、“テーマに関わるキャラクター”です。
『ゆるキャン△』の場合、アニメの第1話では志摩リンがソロでキャンプをしていました。
そこに、各務原なでしこが登場。アウトドア素人である彼女がこの出会いを通し、アウトドアに興味を持ちます。
一方が手慣れていて、もう一方が素人だからこそ、“教える”というシチュエーションの中でネタを“描く”ことが出来ます。
キャラクター同士の絡みの中で

その際に重要なのは、“面白い”こと。
外で食べるカップ麺の美味しさを表すのに、美味しそうに食べるなでしこの食事シーンが描かれました。
前後の会話のやり取りも含め、あくまでそれは“面白可愛い女の子たちのやり取り”のシーンです。
テーマ(題材)に関する知識ネタは、それを表現するための手段の一つ。たとえテーマが“アウトドアの面白さ”であったとしても、そこを前面に出しすぎると、作品としての面白さが欠けてしまいます。
また、志摩リンはソロキャンパーです。
他にも、「野外活動サークル」のメンバーが登場します。
“アウトドア”に関わるキャラクターを出しつつも、それぞれ“アウトドア”への向き合い方が違います。
ここをいかにうまく描き、キャラクターの個性を出せるかも重要です。
一話ではキャラクターを出しすぎない方がベター?
実際の構成を見ていきます。
先述した通り、『ゆるキャン△』の第1話ではリンとなでしこの出会い、なでしことアウドドアの出会いが描かれました。
続く第2話にて、なでしこが高校で「野外活動サークル」(野クル)に出会い、他のメンバーと意気投合します。
1話でいきなり4人出すよりかは、キャラクターを覚えやすい構成です。
『ラーメン大好き小泉さん』の場合でも、第1話は主人公である小泉さんと、もう一人の主人公的存在である大澤 悠を中心に描いています。
この二人のキャラクターと、ラーメンへの想い、ラーメンに関するお話なのだという掴みを行います。
続く2話で残る中村 美沙、高橋 潤のエピソードを行っています。
まとめると

ここまでをまとめると以下のようになります↓
1話:主人公とヒロインが出会い(orそれに近い人物)、“テーマ”に興味を覚える。二人を中心に描く。
2話:他メンバーが登場し、彼女らのエピソードに触れる。
よくいうアニメ一話切り層は、
「いきなり用語だらけ」「1話からキャラ多くて覚えらない」=面倒
と判断して、アニメを切ってしまうパターンが多いと思います。
もちろん、1話からキャラクターが多くても、説明から入っても、魅せ方によっては面白く出来ます。
しかし、1話目のキャラクター数はおさえた方が、入りやすいのです。
さらにまとめると、
“スタートは主人公×ヒロイン(あるいはそれに近い人物)だけで描く方が無難”、“テーマ・題材に関わるキャラクターを使い、面白くネタを出そう”です。
以上までの要素を踏まえ、実際に何かを題材にした作品(小説だったり、漫画だったり)を作る場合の“構成例”を見ていきたいと思います――が!
長くなったので次の機会にでも。