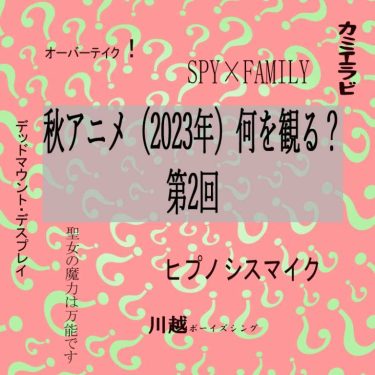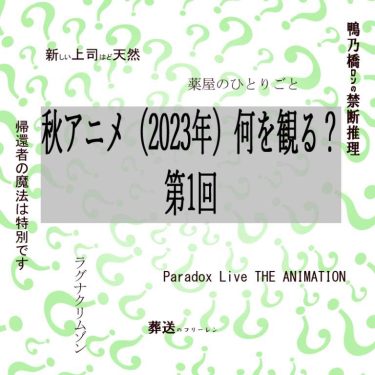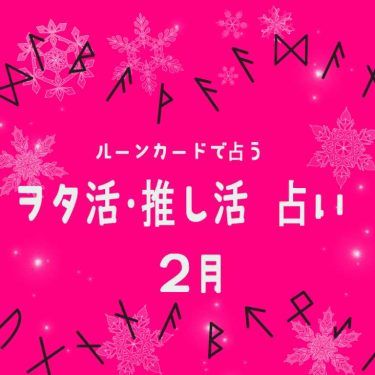「 キラキラ プリキュア アラモード 」、終わってしまいましたね。一年間ありがとうございました。娘を持つ身として、この一年も大切に楽しませていただきました。
そんな最終話放送後、筆者の育児用ツイッターアカウントのタイムラインでこんな呟きが流れてきました。
「うちの子が最初に見るプリキュアが、この作品でよかった」
おや? と思いました。
というのも、筆者自身、長女が最初に触れたプリキュアが「 Go! プリンセスプリキュア 」だったことに深く感謝しており、また翌年の「 魔法つかいプリキュア! 」でも同様の呟きをタイムラインで見た覚えがあったからです。
筆者が気付かなかっただけで、それ以前から同じ呟きがいろんなところで零れていたのかな、と思うと、少し不思議な気がしました。
もちろんプリキュアに限らず、同じく毎年テーマもメンバーも変わる仮面ライダーシリーズやスーパー戦隊シリーズも同じことが言えると思います。
しかし今回は母親の立場として、(初代とプリキュア5を除き)毎年メンバーやテーマが変わる「 プリキュアシリーズ 」がなぜこんなに母親を感動させるのかを個人的見解で書かせていただこうと思います。
プリキュア は毎年違うメンバー、違うテーマだからこそ教えてくれることも違う
まず最初に思い至ったのが、上記表題です。
当然と言えば当然すぎることですが、最終回で伝わってくる「このプリキュアが伝えたい大事なこと」が、「親が子どもに伝えたいと思える大切なこと」だから、娘とともに一年間視聴を続ける親の胸を打つんだと思います。
そして多くの場合、「娘が初めて一年を通して見続けることができた作品」というバイアスもあるでしょう。一人の大人として嗜好から視聴するのではなく、親という立場になって初めて、子どもを見守りつつ視聴するというのはまた違った感慨がありました。
その中で、近年のプリキュア三作品が最終回で示唆してくれたテーマを見てみると、
「 Go! プリンセスプリキュア 」は夢の隣に絶望があることを肯定し、必ずしも恐怖するものではないと教え
「 魔法つかいプリキュア! 」ではどんなに遠い場所への別離でも、それが決して永遠ではないことを示唆し
「 キラキラ プリキュアアラモード 」では、次代があるからこそ未来に行けるのだということを説いた。
筆者はそう解釈しています。
言葉で表現するにはあまりにも陳腐でうさんくさく思えるものばかりですが、「 プリキュア 」という彼女たちが一年間を通して必死に戦い、悩み、涙し、優しくあったからこそきっと娘の胸にもなにか響いてくれているはずと思えるのだと思います。
さて、では実際のところは

実際、子どもたちの胸にどこまで彼女たちの言葉が残っているか、それは分かりません。
それでも、初めて自分の意思で見続けた「 プリキュア 」が、子どもたちにとって特別なものであることは確実なようです。
それというのも、幼稚園のお誕生日会、将来なにになりたいかを毎回発表するのですが、女の子の夢は大半が「プリキュアになりたい」。
しかしもっと詳しく聞いてみると、お姉ちゃんがいる子がなりたいプリキュアは「キュアハート」(ドキドキ! プリキュア)。うちの長女は今も「キュアフローラ」。他の子たちも、自分が最初に見たプリキュアになりたがっているんです。
家で繰り返し録画を見るのも、やはり最初に見たプリキュアが多いようです。
それ以降のプリキュアも録画しているのに、なんだかんだと再生をねだられるのは最初のプリキュアで、親たちは「そろそろ見飽きてきたけれど、仕方ないかもね」という会話も交わしたりしています。
母親は娘と一緒に過ごす時間が父親よりも長いことが多く、従って一緒に録画を見返す機会も豊富です。
娘とともに「作品の良さ」や、最終回で語られる作品テーマも共有しています。
「娘にとって初めてのプリキュア」は、言い換えれば「母親として初めてのプリキュア」でもあるはず。
2つの意味で最初となる作品が誰かのために戦うプリキュアであるかぎり、これからも「娘の最初のプリキュアがこの作品でよかった」という言葉はどこかで呟かれ続けることと思います。