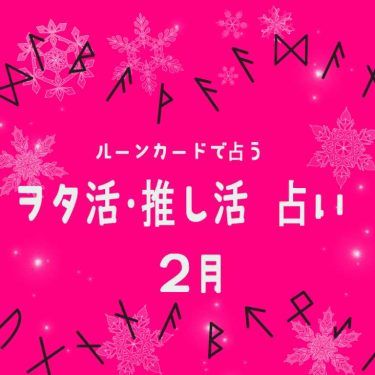先日、人気漫画のアニメ化決定情報がTwitterで拡散され話題になりました。
しかし、後にその情報は発売日前の雑誌に掲載された情報(いわゆる「早バレ」)であることが判明。
最近「ネタバレ」と区別されよく聞くようになった「早バレ」ですが、一体何が問題なのでしょうか。
そもそも「早バレ」とは?

「早バレ」とは、公式の情報解禁よりも前にその情報を勝手に発表してしまうことを指します。
前述のような発売日前の雑誌や書籍の内容をフラゲなどで早めに手に入れた人が拡散する、公式関係者が関係者しか知り得ない情報を漏洩してしまうなどが「早バレ」と呼ばれる行動です。
「ネタバレ」との大きな違いは、公式情報解禁直後に拡散されるのが「ネタバレ」、解禁前に拡散されてしまうのが「早バレ」です。
「早バレ」は何がいけない?
「早バレ」が何かについてはご理解いただけたと思いますが、では「早バレ」の何が問題なのでしょうか。
ここでは雑誌での「早バレ」に焦点を絞って説明しましょう。
本来私たちは、雑誌という「紙」ではなくその紙に記載されている「情報」に対価を払い雑誌を購入しています。
つまり「早バレ」で拡散されてしまった情報は本来雑誌を購入した人が対価(=お金)を払って得るべきものであり、それが無償で拡散されたために発売日に雑誌を買おうと思っていた人が買わなくなってしまう可能性があるのです。
これは言ってしまえば一種の情報漏洩であり、公式関係者の利益を損なう行為です。
早バレの情報がいくら拡散したところで、公式に利益がなければ(この場合なら雑誌が売れなければ)人気のないコンテンツと判断されてしまい、今後の展開が見込めないこともあるのです。
また、当たり前のことですが本来発売日前の雑誌を販売・購入することはルール違反です(都心部ではまれに発売日前に店頭に並んでいることもありますが、本来はルールに反する行為であり、「早バレ」などによる情報漏洩が続くとなくなってしまう可能性も充分ありえます)。
「早バレ」を見分ける方法
拡散されている情報が「早バレ」かどうかを見分けるには、まずは拡散元をチェックしてみましょう。
拡散元が公式サイドではなく、かつ公式サイドから何の情報もない場合、「早バレ」情報である可能性があります。
「早バレ」かもしれないという情報が拡散されているのを見つけても拡散しない、というのも重要です。
もしも拡散してしまってから「早バレ」情報だと知った場合は、拡散(TwitterであればRT)を取り消す、「早バレ」情報に関する発言を削除するなどしましょう。
「早バレ」は犯罪です。
大好きなコンテンツのためにも情報解禁日はしっかり守り、解禁されてから皆で盛り上がりたいですね。
Photo on Visualhunt