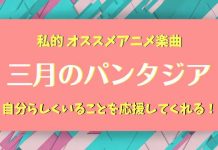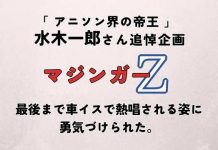アニメ「ヤッターマン」に登場するドロンジョ一味は、奇妙なほど壊れない三人組だ。
悪だくみをしては敗北し、空へ吹っ飛ばされる。その結末を何度も何度も繰り返しながら、彼らは解散しない。交代もしない。新メンバーも入ってこない。ずっと、ドロンジョ、ボヤッキー、トンズラーのままだ。
なぜこの三人の関係は、ここまで安定しているのか。
そこにあるのは、色恋でも、単純な主従関係でもない。むしろ、「恋にもならない好意」と「上司とも家族ともつかない距離」が絶妙に絡み合った、心理学的に見てかなり複雑な共同体である。
このコラムでは、とくにボヤッキーとトンズラーの「献身的な行動原理」に焦点を当てながら、ドロンジョ一味という不思議な関係の深層をたどってみたい。

ドロンジョは「支配者」ではなく、感情の投影先である
まずはボスであるドロンジョの立ち位置を整理してみる。
彼女は一味のリーダーだが、圧倒的な有能さでメンバーを従えるタイプではない。作戦はどこか大雑把で、感情的に怒り、負ければ部下に八つ当たりもする。冷静な戦略家というより、「勢いと責任を背負う役」を押しつけられている人、という印象すらある。
しかし、ボヤッキーとトンズラーの視線で見ると、彼女はただの上司ではない。そこには理想化された「女ボス」や、「叱ってくれる大人」、「自分たちを導いてくれる象徴」など、さまざまな意味が重ねられている。
心理学の言葉で言えば、ドロンジョは二人にとって「投影のスクリーン」である。自分が欲しいリーダー像、自分が守りたい存在、自分が仕えたい“何か”を、彼らはドロンジョというキャラクターに映し出している。だからこそ、彼女は完璧でなくてもよいし、むしろ欠点があるからこそ「自分たちが支えなければ」という感情が強まっていく。
ボヤッキーとトンズラーの献身は、「安全な片思い」から生まれる
では、その支えたいという気持ち、あれほどの献身はどこから湧いてくるのか。
ボヤッキーのドロンジョへの態度は、明らかに好意を帯びている。甘い言葉をささやき、メカを設計し、彼女のために毎回全力を出す。一方、トンズラーもまた、敵に吹き飛ばされる瞬間までドロンジョをかばい、いつもそばにいる。二人の行動原理には、確かに「好き」という感情がある。
しかし、よく見るとそれは、成就を求める恋愛とは少し違う。
彼らは、自分の想いがドロンジョに返ってこないことを、どこかで理解している。期待しているようで、あきらめている。あきらめているようで、「まあ、別にこのままでもいいか」と受け入れている。
この構造は、心理学的には「安全な片思い」と呼べる。
きちんと距離が保たれた一方通行の好意は、相手に依存し過ぎず、自分の存在を支える柱にもなりうる。ボヤッキーやトンズラーにとって、ドロンジョに仕えることは「自分がここにいていい」と感じられる拠点であり、同時に「自分の役割と価値」を実感できる場所でもある。
献身は、見返りがないからこそ純度が増すときがある。
見返りを求めた瞬間、それは取引になる。ボヤッキーとトンズラーの愛情が、恋愛よりも“信仰”や“推し活”に近いニュアンスを帯びるのは、そのためだろう。自分のエネルギーを捧げている感覚そのものが、彼らにとっての報酬になっている。
敗北の共有がつくる「心の共同体」
もうひとつ、三人の結束を語るうえで欠かせないのが、「失敗の反復」である。
毎回ヤッターマンに負ける、空へ吹っ飛ばされる、ボロボロになって落ちてくる。このループは笑いの定番として描かれているが、心理学的にはかなり大きな意味を持つ。失敗を一緒に経験し、その責任を分かち合い、同じ痛みを味わう。これを繰り返すことで、人は「自分は一人ではない」と深く感じるようになる。
通常、失敗は人間関係を壊す方向に働きがちだ。
しかし、ドロンジョ一味の場合は真逆である。どれだけ大敗しても、翌週にはまた同じテントで作戦会議をしている。敗北は恥ではなく、三人だけが共有する“儀式”のようになっている。ここに、「一緒に負けても関係は終わらない」という強い確信が生まれる。
この確信は、心理的な安全基地と言い換えられる。
成功したときよりも、失敗しても関係が続くとわかっているチームのほうが、実はずっと深くつながっている。ボヤッキーとトンズラーがドロンジョのために何度でも立ち上がれるのは、「どうせまた三人で吹っ飛ぶだけ」という妙な安心感が、心のどこかにあるからかもしれない。
恋愛を“封印”することで続いていく関係
ここまで見てくると、ドロンジョ一味が暗黙のうちに共有している「禁忌」がひとつ浮かび上がってくる。
それは、「この関係を恋愛として成立させてはいけない」という、言葉にならない合意だ。
もしドロンジョがボヤッキーと特別な関係になれば、トンズラーとのバランスは崩れる。
どちらか一人だけが選ばれれば、残された側には耐えがたい疎外感が生まれる。三人の間に、上下や優先順位がはっきりと刻まれてしまう。そうなれば、この奇妙に水平な共同体は、もはや今の形ではいられない。
だからこそ、三人は無意識に恋愛への一歩手前でブレーキを踏み続ける。
ボヤッキーとトンズラーは、冗談めかして口説き、ドロンジョはツッコミながら受け流す。このやりとりを繰り返すことで、感情はガス抜きされ、しかし決して“決定的な一線”は越えられない。
献身の原理は、実はここにもある。
成就しないからこそ燃え続ける感情。
終わらない片思いだからこそ守られるバランス。
約束されない見返りだからこそ純度を保つ忠誠。
三人は本能的に、それを壊した瞬間、自分たちの居場所も消えてしまうことを知っているのかもしれない。
本当にドロンジョには「その気持ち」はないのか?
最後に、いちばんやっかいで、いちばん魅力的な問いに戻ってみる。
ドロンジョの心には、本当に何の恋愛感情も、特別な情もないのだろうか。
行動だけを見れば、彼女はしばしば自分勝手で、部下に怒鳴り、失敗の責任を押しつけるような態度も取る。しかし、そのあとで必ず同じ場所に座り、同じ食事をし、同じ敵と向き合い、同じタイミングで空へ吹っ飛ばされる。彼女は一度も、ボヤッキーとトンズラーを見捨てて逃げたりはしない。
それを、単なる「悪役の様式美」として片づけることもできる。
けれど、心理学の視点から見れば、これはかなり濃度の高い共同体的愛情のかたちでもある。母親にも恋人にも上司にも言い切れない、分類不能な情のあり方。彼女がその感情に、どんなラベルを貼っているのかは、作品の中では語られない。
だからこそ、視聴者は何度も同じパターンを見ながら、自分なりの解釈を重ねていく。
ドロンジョは本当は二人を愛しているのかもしれない。
いや、むしろ「愛しているなんて言葉で片づけたくない」と思っているのかもしれない。
それとも、そんなことを考えたことさえないのかもしれない。
どの解釈も、完全には否定できない。
どの解釈も、完全には証明できない。
ボヤッキーとトンズラーの献身は、
ドロンジョに向けられているようでいて、
同時に「三人でいられる自分」に向けられた愛情でもある。
そしてその愛情に、ドロンジョがどう応えているのか。
そこに「その気持ち」があるのか、ないのか。
その答えだけは、きっと彼女の内側にしかない。
視聴者はただ、その沈黙のまわりをぐるぐると回りながら、
三人の姿を見上げ続けるしかないのだろう。
吹っ飛んでいくシルエットが、なぜか少し温かく見えるのは、
その「答えのなさ」そのものが、
私たち自身の人間関係のあいまいさとどこか重なっているからかもしれない。
イラスト:デコポン